�@(k)�@�r���ƁA���₢���̃��[�h�̂��߂�(�Œ�̂��߂ł͂Ȃ�)
�o�E�E�g�����T���̂������
�̑O���K���l����ʂ̒��S����Ɍ��P��(���a�ő�8mm)�B
�r���A�y�уt�b�g�x���g�Ƀe���V����
�������邽�߂̃V���b�N�R�[�h������ꍇ�͂��̌Œ�̂��߂ɁA�X�^�[���E�g�����T���̂����O
�̌㕔�K���l����ʂ̒��S����ɁA���P��(���a�ő�8mm)�B
( �K��4.3 ���Q��) �r���p�ɁA�_�K�[
�{�[�h�X���b�g�㕔�́A�_�K�[�{�[�h�P�[�X�̏�ʂ̒��S����Ɍ��P��(���a�ő�8mm)�B�@�@�@�@�@
3.2.6.2
�@�����͂f�q�o���ł͐}�ʂ̒ʂ�ɁA�܂��A���}�̂悤�ɖ��ߍ���Ŏ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�i�����A�����̏�ʂ́A�D��t�H�[���R�A�̏�ʂƓ����ʂł��邱�ƁB�j�t�b�g�x���g�̓~�h�V�b�v
�t���[���ɁA�ō��S�̃v���[�g�i�e�x���g�ɂQ�j���A�����Ȃ�ő吡�@50mm�}10�~20mm�}5�~
2mm�}1�A�v���X�`�b�N�Ȃ�P��50mm�}10�~50mm�}10�~�Xmm�}1�̂��̂𗘗p���Ď��t���Ă��悢�B�@

3.2.6.3�@���̊e���ƁA�K���ɓ��ɋ�����Ă��Ȃ����̍��ڂ́A�֎~����F
(a)
���C���V�[�g�E�N���[�g�A���C���V�[�g�E�z�[�X�A�g���b�N���̓g���x���[�B
(b)
�z�����x�C���[�y�уr���W�|���v�B
(c)
�b�A���͊e��̃X�v���[�J�o�[�B
(d)
���O���͌��O�ɒ���o�������͍l�Ă������̂ŁA�w�����X�}�������O�ɏo���
�������邽�߂Ɏg������́B
3.2.7 �@�@���@��
3.2.7.1�@ ���̂ɂ́A���x�̂���@�ۂŕ⋭���ꂽ�ގ��̕��͗p�G�A�o�b�O���A���͑̂Ƃ��ĂR�t���Ȃ���
�@�@�@�@�@�@�@ �Ȃ�Ȃ��B�e���͑̂́A��C�̋��R�̕��o���m���ɖh�~����o���u������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@�@�@�@
�i�����A��C�R��h�~�o���u����т˂����L���b�v�̃o���u�j�B�e���͑̂́A45�}5 د�قłȂ���
�@�@�@�@�@�@�@ �Ȃ�Ȃ��B�e���͑̂̍ŏ��d�ʂ́A200�O�����Ƃ���B
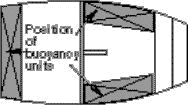 |
3.2.7.2 �@ ���͑̂̂P�́A�X�^�[���E�g�����T���̑S���ɂ킽���Ď�t���A���̕��͂��ꂼ��
�~�h�V�b�v�t���[���ƃ}�X�g�X�I�[�g�u�ǂƂ̊Ԃ̗����Ɏ�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.2.7.3�@�@���͑̂́A���ꂼ��R�{�́A��45mm�}6 �̃X�g���b�v�Œ��̂Ɉ��S�ɌŒ肵�Ȃ����
��Ȃ��B�f�q�o���ł́A�e�X�g���b�v�̌Œ�ɂ́A�������Ȃ�P��50mm�}10�~20mm�}5�~2mm�}1��
�����ƁA�P��50mm�}10�~20mm�}5�~2mm�}1�̌Œ����A�܂������v���X�e�B�b�N�Ȃ�P��50mm�}
10�~20mm�}5�~�Xmm�}1�̔��A�g�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�㕔�g�����T���̃Z���^�[�X�g���b�v�́A
���傫���P��50mm�}10�~50mm�}10�~2mm�}1�̋������A�܂������v���X�e�B�b�N�Ȃ�P��50mm�}
10�~50mm�}10�~�Xmm�}1�̔��A�t�b�g�x���g�Ɍ������Ďg�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.2.7.4 �@�I�[�i�[�́A���͂ɂ��Ă͏�ɐӔC�������A12�P���ȓ��Ɋm�F���s���A���͂̎������s
���āA�v�������͐ӔC�̂���N���u�̃I�t�B�T�[�Ɍv���ؖ����ɗ����������Ă��炤�ӔC������B�v��
�ؖ����͗����������܂ŗL���ł͂Ȃ��B
3.2.7.5�@�@
�v�����́A���̕��͎����ɗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��F
�~�h�V�b�v�t���[����� 100mm�ȓ��̌����60kg�ȏ�̓S�̏d�ʕ���u���āA�{�[�g��Z����������
���A�K���l�������ʏ�ɏo�ĕ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�����́A���͑̂Ƃ��̎�t�������m����
����A�c�����̕��͑̂ł́A��C�̔����钥��̗L�������F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.2.7.6�@�@�ŏ��̕��͎����́A�ŏ��ɒ��̌v�����������_�Ő��K�ɍs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����v
���������̎��_�ŕ��͎������s���Ă��Ȃ����Ƃ��ؖ�����ꍇ�́A���̃N���X�K���̍ו��S�Ă�����
�ł����Ă��A�v���ؖ����ɂ́u���͎����ɍ��i�����Ƃ����m�F�͂Ȃ��v�Ƃ�����������t�����s����
��B
3.2.8 �@�@�@�d�@��
3.2.8.1�@�@
���̂̏d�ʂ́A������ԁA�����L�̏�Ԃ�32kg �ȉ��ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�@�@�@ �@���̂��̂��܂��F�X�^�[���E�g�����T���ɌŒ肵�Ă��郉�_�[����A���͑̃X�g���b�v�A�t�b�g
�@�@�@�@�@�@�@�@ �x���g�ƁA���̎�t�~���i�i���O���\�����A�̂�ی암�i�������j�A�}�X�g�X�e�b�v�A�i�v
�@�@�@�@�@�@�@�@ �I�ɌŒ肳�ꂽ�u���b�N��t�~���i�B�@���̂��̂������F��d�ʕ��A�u���b�N�A���C���V�[�g
�@�@�@�@�@�@�@�@ ���͗p�G�A�o�b�O�A���₢���A�x�C���[�A�p�h���A�R���p�X�Ƃ��̌Œ葕�u�i�u���P�b�g�t����
�@�@�@�@�@�@�@�@ ���̂͂�����܂ށj�A���{�g���p��t�N���b�v�A�H���e��₻�̑��l�̔��i�A�y�сA���ɋ���
�@�@�@�@�@�@�@�@ ����Ă��Ȃ����B
3.2.8.2 �@ �K��3.2.8.1 �ɒ�߂�ꂽ��Ԃ̒��̂ɁA���͗p�G�A�o�b�O����������Ԃ̏d�ʂ��A
35kg�����A32.6kg �ȏ�̏ꍇ�́A�d�ʂ� 35kg �ȏ�ɂȂ�܂Ŗؐ��̕�d�ʕ�����̂ɌŒ肵�Ȃ�
��Ȃ�Ȃ��B��d�ʕ��́A�������o�E�E�g�����T���ɁA�������X�^�[���E�g�����T���ɁA�i�v��
�Œ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��d�ʕ��́A���K�̌v�����ɂ���Ē��̂̍Čv�ʂȂ��ɁA�����������
�X���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�e��d�ʕ��̏d�ʂ́A���͑��̕��@�ŕ�d�ʕ��Ƀ}�[�N���A�v���ؖ���
�ɗ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�K��3.2.7.1 �̕��͗p�G�A�o�b�O�̍ŏ��d�ʂ��Q�Ɓj
3.3.1
�ށ@��
3.3.1.1 �@ �_�K�[�{�[�h�́A�ȉ��̍ޗ��A�������͂�����g���������̂ō��Ȃ���Ȃ�Ȃ��F
|
�@�� |
�@���܂��͐ϑw�� |
|
GRP�@�@�@�@ |
|
|
�@���� |
�@��ނ���Ȃ��B���F�Ɍ��� |
|
�@�K���X�@�� |
�@��ނ���Ȃ��B���F�Ɍ��� |
|
�@�t�H�|���ށB �c�ނƂ��Ă̂ݎg�p�@ |
�@��z�������Z���A��ނ���Ȃ��@ |
|
�@�ڒ��� |
�@��ނ���ѐF����Ȃ� |
|
�@�[�U�� |
�@��ނ���ѐF����Ȃ� |
|
�@�Q���R�[�g�܂��͓h���@ |
�@��ނ���ѐF����Ȃ� |
3.3.1.2 �@���a20mm�ȉ��̔�����⋭�ށi�u�b�V���j���A�˂�����x�b�g����̓{���g�̎��͂Ɏg���Ă��悢�B
3.3.2 �@�@ �`�@��
3.3.2.1�@ �_�K�[�{�[�h�́A�����̃R�[�i�[�a32mm�ȓ��A�㕔�̃R�[�i�[�a�Tmm�ȓ��Ŋۂ߂Ă��悢
�@�@�@�@�@�@�@���́A�����`�̕��łȂ���Ȃ�Ȃ��B
3.3.2.2�@ �_�K�[�{�[�h (�x�x��������) �̌����́A10mm�ȏ�A14mm�ȉ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B�x�x
�����F�߂���̂́A�e�����Ɗe��������60mm�̉ӏ��ɐ݂���ꂽ�x�x�����E�ʒu�Ƃ̊ԂƂ���B�@�x
�x�����E�ʒu�Ԃ̃_�K�[�{�[�h�̌����́A�ǂ̉ӏ��ɂ����Ă�0.5mm���z���鍷�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.3.2.3�@ �_�K�[�{�[�h�̑S����1067mm�ȉ��A���� 290mm�ȉ��A275mm �ȏ�łȂ���Ȃ�Ȃ��B��
���̐����̓��A���͂Rmm���z���ĕω������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.3.2.4 �@�_�K�[�{�[�h�ɂ́A�{�[�h�̏㕔���ʂɃX�g�b�v�E�o�e���i���Ėj����t���Ȃ����
��Ȃ��B�@�@�@�o�e���Ƃ��ĔF�߂���ގ��́A�_�K�[�{�[�h�Ɠ���Ƃ���B�o�e���̓{�[�h�̑S����
�y�Ԃ��̂ŁA�[���͑S�ʂɓn����35mm�ȏ�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�o�e���ƃ_�K�[�{�[�h�̍��v������
�A40mm�ȏ�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�I�o�����o�e���̉����́A���a�Tmm���z���Ȃ��͈͂Ŋۂ߂Ă��悢�B
�o�e���͐ڒ��܋y�с^���͒��a10mm�̂Q�{�ȓ��̃{���g���͂��̏d�ʂ��z���Ȃ��͈͂ŁA�����菬��
���{���g�A�s���A���x�b�g�A���͖˂��ŌŒ����邱�Ƃ��ł���B�����Œ��B�̒����́A�_�K�[�{�[
�h�ƃo�e����g�ݍ��킹���������z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̑��A�o�e�����_�K�[�{�[�h�ƈ�̂ō���Ă�
�悢�B
3.3.3 �@�@�_�K�[�{�[�h�̏d�ʂ́A��t������̂�Œ肷����̂������āA�Qkg�ȏ�łȂ���Ȃ��
���B�_�K�[�{�[�h�Ƀo���X�g��t������A�蔲�����肷�邱�Ƃ́A�֎~����B�@�_�K�[�{�[�h�ƃo�e
����g���������̂̏d�S�́A�������� 520mm�ȏ�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.3.4 �@�@�_�K�[�{�[�h�͕������̂Ƃ��A���Ɏ�t���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�_�K�[�{�[�h�ƃo�e��
���ђʂ��錊���A�K���ȏꏊ�ɂP�A�����Ă��悢�B���̒��a��10mm���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�_�K�[�{�[
�h����̂Ɏ�t���邽�߂ɁA�e���R�[�h���̓��j���[�h���g�p���Ă��悢�B�R�[�h��j���[�h���A��
�́A���̓_�K�[�{�[�h�Ɏ��t���邽�߂ɁA�P�̏������V���b�N�����g�p���Ă��悢�B
3.3.5 �@�@�_�K�[�{�[�h�́A���[�v��́i�e���j�R�[�h��p���ă_�K�[�{�[�h�P�[�X���ɕێ��������
���悢�B�R�[�h�́A�Q�̃A�C��ʂ��ă_�K�[�{�[�h�P�[�X�ɌŒ肷�邩�A���͂Q�̒��a10mm�ȓ���
����ʂ��ă}�X�g�X�I�[�g�u�ǂɌŒ肵�Ă��悢�B�A�C���͌��̈ʒu�́A���R�ł���B
3.4.1 �@�@�ށ@��
3.4.1.1 ���_�[�́A�ȉ��̍ޗ��A�������͂�����g���������̂ō��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
�@�� |
�@���܂��͐ϑw�� |
|
GRP |
|
|
�@���� |
�@��ނ���Ȃ��B���F�Ɍ��� |
|
�@�K���X�@�� |
�@��ނ���Ȃ��B���F�Ɍ��� |
|
�@�t�H�|���ށB �c�ނƂ��Ă̂ݎg�p�@ |
�@��z�������Z���A��ނ���Ȃ��@ |
|
�@�ڒ��� |
�@��ނ���ѐF����Ȃ� |
|
�@�[�U�� |
�@��ނ���ѐF����Ȃ� |
|
�@�Q���R�[�g�܂��͓h���@ |
�@��ނ���ѐF����Ȃ� |
3.4.1.2 �@�e�B���[�ƃe�B���[�G�N�X�e���V�����́A�����Ȃ�ގ��ō���Ă��悢�B
3.4.1.3 �@���a20mm�ȉ��̔�����⋭�ށi�u�b�V���j���A�˂�����x�b�g����̓{���g�̎��͂Ɏg���Ă��悢�B
3.4.2 �@�@�`�@��
3.4.2.1�@
���_�[�̌`��͎��R�ł��邪�A���_�[��t������������āA750mm�~260mm�̒����`�̒���
���܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@���_�[�w�b�h�Ƃ́A���̒����`�̏㉏����300mm�ȓ��ɂ��郉�_�[�̕�����
���Ƃł���B���_�[�̎c��̕����́A���_�[�u���[�h�ł���B
3.4.2.2 �@���_�[�u���[�h�i�x�x���������j�̌����́A10mm�ȏ�A14mm�ȉ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B�x
�x�����F�߂���̂́A�e�����Ɗe��������60mm�̉ӏ��ɐ݂���ꂽ�x�x�����E�ʒu�Ƃ̊ԂƂ���B�x
�x�����E�ʒu�Ԃ̃��_�[�u���[�h�̌����́A�ǂ̉ӏ��ɂ����Ă�0.5mm
���z���鍷�������Ă͂Ȃ�Ȃ�
3.4.2.3 �@�e�B���[�ƃe�B���[�G�N�X�e���V�����y�ѕt���̎�t������ނ́A�ǂ̂悤�Ȍ^���ł���
�����A��������s���ˋN�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.4.2.4 �@�e�B���[�ƃe�B���[�G�N�X�e���V�����́A���ꂼ��̒�����
750mm���z���Ă͂Ȃ炸�A��
����g�����������́A1200mm���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.4.2.5�@���_�[�w�b�h�t�����g���C��(�K��3.4.4 �̒�`�Q��) ���������̃e�B���[�A���̓G�N
�X�e���V�����̂ǂ̕������A�����`(3.4.2.1�Œ�`)�Ɏ��܂�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.4.3 �@ ���_�[�A�e�B���[�y�уe�B���[�G�N�X�e���V������g���������̂́A�����Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A
�܂��A�����̑��d�ʂ�1.5kg�ȏ�łȂ���Ȃ�Ȃ��B������g���������̂̂����Ȃ镔���ɂ��A�o
���X�g��t���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.4.4 �@�@���_�[�\���v�f�̒�`
3.4.4.1 �@�x�A�����O���C��
�F ���_�[�ɕt���Ă���x�������ʂ�Q�{�̐������i����ɕ��s�j
3.4.4.2 �@���_�[�w�b�h�t�����g���C��
�F ���_�[�̑O���ƂQ�{�̃x�A�����O���C������������e�_��ʂ���B
3.4.5�@�@
��t���y�шʒu����
1992�N�R���P���ȑO�Ɍ������ꂽ���ɂ��ẮA���������ɐ����ł��������_�[�̈ʒu���ߕ��@�ł��A
���s�̕��@�ł��悢�B���̏ꍇ�A���_�[�̎�t������̂̈ʒu���߂́A���_�[�Ɋւ��铖���̋K����
�]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.4.5.1 �@�Q�̃s���g�������_�[�ɌŒ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�s���g���̒��a�́A���̂Umm�ȉ���
�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�e�B���[�̏㉏�Ə㕔�s���g���̃x�A�����O���C���Ƃ̋����́A���_�[�w�b�h�t��
���g���C���ɉ����đ�����85mm�ȏ�łȂ���Ȃ�Ȃ��B���a�Umm�ȏ�̌����������Q�̃K�W������
�X�^�[���E�g�����T���ɌŒ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Q�̃K�W�����̃x�A�����O���C���Ԃ̋����A
200mm�ȏ�łȂ���Ȃ�Ȃ��B����ɑ���s���g���Ԃ̋����́A200mm
�ȉ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�Q�̃K�W�����x�����̌��̐[���͂Tmm���z���Ȃ����̂Ƃ��A�����̌�����X�^�[���E�g�����T����
��ʂ܂ł̋����ɂ͂Qmm���z���鍷�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.4.5.2 �@���_�[�ƃe�B���[��g���������̂́A�X�^�[���E�g�����T���Ɏ�t���A�]�����ɒ��̂���
����Ȃ��悤�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@���̂��߂ɁA�K�ȃN���b�v���̓X�v�����O�����_�[�w
�b�h�O���̏㕔�s���g���̃x�A�����O���C�����牺���Tmm�ȏ�̂Ƃ���Ɏ�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.4.5.3 �@�X�^�[���E�g�����T���Ɏ�t����ꂽ�ꍇ�A���_�[�w�b�h�t�����g���C������X�^�[���E
�g�����T���̌�ʂ܂ł������́A�Q�{�̃x�A�����O���C���̈ʒu�ő�����40m���z���Ȃ����̂Ƃ��A��
���Qmm���z���鍷�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
<div align="right"></div>3.5 �@�@�@�X�p�[ ��
3.5.1 �@�@�ށ@��
3.5.1.1 �X�p�[�ނ́A�A���~�j�E�������ǖ��͒����̖؍ނō��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ؐ��̃X�p�[
�́A�Q�Јȉ��̖łȂ���Ȃ�Ȃ��B���e�덷������~�`�A�e�[�p�[���͑��̕��@�ŕό`������
�X�p�[�ނ́A�����Ȃ���̂ł��֎~����B�A���~�j�E�������ǂ̓����́A���������S�̂ɂ��ċψ��
�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̃X���[�u�A���u�A�y�ѕ⋭�ނ́A�֎~����B
3.5.1.2 �@�u�[���̃W���[���܂ރG���h�L���b�v�Ȃǂ��~���i�́A�v���X�`�b�N�A�A���͋����̂�
����ō���Ă��悢�B�G���h�L���b�v�A�X�v���b�g�G���h�y�уW���[��t���́A�X�p�[�ɉi�v�ɌŒ肷
�邩�A�ڒ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������~���i�y�уL���b�v�̒����́A�}�X�g�̉��[�y�уu�[����
�W���[�̊O�[����100mm�A�}�X�g�̒����y�уX�v���b�g�̗��[����
60mm�A���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�}�X�g
�����ɂ�����G���h�L���b�v�̎��F�ł��镔���̍����́A10mm���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.1.3 �@�X�p�[�ނ́A�����ȐZ���������悤�ɖ����ꂽ�`�����A�l�ߍ��܂ꂽ���A�̂ɂ���ĕ�
�͂��ێ�����`���ł���A�����悻������30���Ԃ͐��ɕ������͂�L���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.5.1.4 �@�����̋K���ɂ���ē��ʂɋ�����Ȃ���A�X�p�[�ނ��~���i�́A���x�b�g�A�l�W����
�{���g�ƃi�b�g�ʼni�v�I�ɌŒ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.5.1.5
�@������ی�ނ́A�ڐG����͈͂ɂ����ăX�v���b�g���̓}�X�g�̂ǂ��炩�Ɏg���Ă���
���B���̍ޗ��́A����150mm�A���� 1.5mm�A���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.2 �@ �} �X �g
3.5.2.1 �}�X�g�́A�f�ʂ��قډ~�`�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�ǂ̒f�ʂ��A���a���Rmm���z���ĕω�����
�͂Ȃ�Ȃ��B�����50mm����̒��a�́A�ǂ��ł�44mm�ȏ�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
3.5.2.2 �@�}�X�g�́A�����50mm����̒f�ʂ͋ψ�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�ؐ��}�X�g�͊��
��800mm�ȓ��Ȃ�A���a�łSmm�ȏ㑝���Ȃ��͈͂ŁA�e�q�o���̓v���X�`�b�N�̃J���[�P�ŕ⋭����
���悢�B
3.5.2.3�@�A���~�E�}�X�g�́A�}�X�g�X�H�[�g�E�z�[���y�у}�X�g�X�e�b�v�ɍ����悤�ȑ傫�߂̒��a
�̂e�q�o���̓v���X�`�b�N�̃J���[���Q�ȓ��ŕt���Ă��悢�B�e�J���[�́A�ψ�f�ʂŁA�}�X�g�ɉ�
����50mm�ȓ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B
3.5.2.4 �@�}�X�g�̑S���́A2350mm���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.2.5 �@�����Ȃ��ނ̃X�^���f�B���O�E���M�����A�֎~����B
3.5.2.6 �@�}�X�g�ɂ́A�����ʂ̂ǂ��炩�̕����ɁA�Q�̌��A���͂Q�̃A�C�i�i�v�I�ȌŒ�ł�
���Ă悢�j�A�������͂P�Â̌��ƃA�C��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�P�̌����̓A�C�̏㉏�́A�}�X
�g��������20mm�ȏ�A���̂P�̏㉏�́A�}�X�g��������120mm�ȏ�A�̈ʒu�łȂ���Ȃ�Ȃ��B��
�b�V���O�E���C���i����݁j�́A�����̃A�C���͌���ʂ��A�Z�[���̃X���[�g�̃A�C���b�g��ʂ���
����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�K��6.6.3.1���Q�Ƃ̂��ƁB�����A���͕�����t���i (�K�� 3.5.2.12)���A�@�@
���b�V���O�E���C�����Œ肵����A���邢�́A���b�V���O�E���C���ɂ���ČŒ肳��邱�Ƃ�����B�������A��
�̎��́A���b�V���O�E���C�����}�X�g�̌����̓A�C�ɒʂ��Ȃ��Ă��悢�A�ƌ������ł͂Ȃ��B
3.5.2.7 �@�ΏƓI�ȐF�ŁA���[�X���ɑN���Ɏ��F�ł��镝10mm�ȏ�̃o���h���A���̂悤�Ƀ}�X�g��
�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��F
(a) �@�@No.�P�o���h�B�o���h�̉����̓}�X�g�������� 610mm�ȏ�Ƃ���B
(b) �@�@No.�Q�o���h�B�o���h�̏㉏�̓}�X�g�������� 635mm�ȓ��Ƃ���B
No.�P�o���h�̉�����No.�Q�o���h�̏㉏�ɂ́A�������ނ��A�Q�ȏ�̃Z���^�[�|���`��ł��ĉi�v�I
�ȃ}�[�N��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.5.2.8 �@�}�X�g�́A�}�X�g�X�e�b�v�ŁA�E�F�b�W�A�u���b�N�A���͑��̑��u���g���ē����Ȃ��悤
�ɂ��A�����̂ǂ̕����ɂ��Rmm���z���ē����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�}�X�g�q�[���̈ʒu
�́A���[�X���͕ς��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.2.9 �@�}�X�g�ɂ́A�u�[���̃_�E���z�[�����Œ肳����K���Ȉʒu�ɁA�N���[�g�P��t���Ȃ�
��Ȃ�Ȃ��B
3.5.2.10 �}�X�g�ɂ́A�X�v���b�g�p�Ƃ��āA�N���[�g�ƂP�̌����̓A�C�i�Œ肷��K�v�͂Ȃ��j
���͎���̊|����̂ǂ��炩��K���Ȉʒu�ɕt���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.5.2.11 �����]���������ɁA�X�e�b�v����}�X�g�������o���Ă��܂��̂�h�����߂ɁA���b�N����
���u���͑��̑��u��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.5.2.12 �}�X�g�����ɕ�����t���Ă��悢�B�����́A�}�X�g�Ɋm���Ɏ��t����i�i�v�I�ɌŒ肷
��K�v�͂Ȃ��j�B�����́A�}�X�g�����̉���150mm�ȓ��ŁA����Ă��Ȃ����̂�t���Ȃ���Ȃ��
���B�������͂��̎�t����́A�Z�[���̃X���[�g���烉�b�V���O�E���C�������t���邽�߂Ɏg����
���悢�B
3.5.2.13 �}�X�g�ɂ́A�}�X�g�������牺��1680mm�}10mm�ȓ��̃}�X�g�̑O���Ƀs���X�g�b�v��ł�
�Ă��悢�B���̃s���͒��a�Wmm�ȓ��ŁA�}�X�g�̕\�ʂ���10mm�ȉ��ŁA����Ă��Ȃ����̂łȂ����
��Ȃ��B
3.5.3.1 �@�u�[���́A�قډ~�`�ŁA�S�̂�ʂ��ċψ�Ȓf�ʂłȂ���Ȃ�Ȃ��B���a�́A25mm�ȏ�
�ł���A�@�ǂ̒f�ʂ��Rmm���z����ω��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.3.2 �@�u�[���́A�u�[���̃W���[�������āA����2057mm���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.3.3 �@�u�[���̃W���[�̌^���y�ю�t�^�͎��R�ł��邪�A�W���[�̌�����35mm���A�W���[��t��
�̒�����100mm���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�P�{�̃��[�v���A�u�[���̃W���[���̓W���[��t���́A�Q�̌���
�͂Q�̃A�C��ʂ��đO�ɉA�}�X�g�O�ʂ̃s�����āA�~�߂Ă��悢�B�i�K��3.5.2.13�Q�Ɓj
3.5.3.4 �@�ΏƓI�ȐF�ŁA���[�X���ɑN���Ɏ��F�ł��镝10mm�ȏ�̃o���h���A���̓������}�X�g��
�㉏����2000mm���z���Ȃ��悤�Ƀu�[���ɕt���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�o���h�̓����́A�������������A�Q
�ȏ�̃Z���^�[�|���`��ł��āA�i�v�Ƀ}�[�N��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�G���h�L���b�v�̎��F�ł�
�Ȃ��������o���h�̑O���������̈ʒu�ɒB���A�L���b�v���g�����̋K���̑O�̕����ƋK��3.5.3.2�̗v
�������Ă���ꍇ�ɂ́A�u�[���O�[�̃J���[�o���h�́A���̃G���h�L���b�v�ɉi�v�I�ɌŒ肵�Ă�
�悢�B
3.5.3.5 �@�u�[�����̓G���h�L���b�v�̂ǂ��炩����ɁA�����͌Ŕ��p�A�C��݂��Ȃ���Ȃ��
���B���̑O���A���̓A�C�̊J���̑O���́A�u�[���O�[���̃o���h�̓�������40mm���z���Ă͂����Ȃ��B
3.5.3.6 �@�u�[���ɃN�����[�E�A�E�g�z�[�����Œ肷�邽�߂ɁA����Ă��Ȃ��N���[�g��t���Ă���
���B����́A�u�[���̊O�[���� 400mm�ȏ�̈ʒu�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
3.5.3.7 �@�u�[���ɌŒ肳�ꂽ�X�g�b�p�[���͈ʒu���Œ肵���A�C���g���āA���R�ȕ��@�Ńu�[���E
�_�E���z�[�����Ƃ��Ă��悢�B�@�����~���i�̊O���́A�u�[���E�W���[�������u�[���̓��[����
200mm
���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.3.8�@
�u�[���Ƀ��C���V�[�g���̓��C���V�[�g�E�u���b�N (����) ���Ƃ���@�́A���R�ł���B
�i�������A�u�[���ɉ����Ĉړ����Ȃ����̂Ƃ��A�܂�������ƃu�[���Ƃ̍ő匄�Ԃ́A�u�[���̂ǂ���
�����Ă�100�o���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��j�u���b�N�̈ʒu���̓u�[���E�X�g���b�v�̒����́A���[�X���ɒ���
���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.3.9 �@�����̋K���Ŗ��炩�ɗv������Ă��邩������Ă��鍀�ڂ������āA�}�X�g�ɑ���
�u�[���̈ʒu�߉\�Ƃ���ړI�̂����Ȃ��~���A���M���A���͑��u���݂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.4
�@�@�X�v���b�g
3.5.4.1 �X�v���b�g�́A�قډ~�`�ŁA�S�̂�ʂ��ċψ�Ȓf�ʂłȂ���Ȃ�Ȃ��B���a�́A24mm��
��ł���A�ǂ̒f�ʂ��Rmm���z���ĕω����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.4.2 �@�X�v���b�g�́A�[�����~���i���܂݁A������2286mm���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.4.3 �@�X�v���b�g�̏�[���~���i�̌^���́A���M���v�����̂悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�n�߂ɍׂ�
��[���~���i��t�����ꍇ�ɂ́A��������ɂ��Ă��A13mm���z���đ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�X�v���b�g�̉��[���~���i�́A��[�ŋ�����Ă�����̂��A�P�̃A�C���̓t�b�N��t���邩�A�����̓X�p�[�Ɍ�����
���邩�A�̂ǂꂩ�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���[���~���i�̒����́A60mm���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�X�v���b�g���[�ɁA�A
�C�A�t�b�N�A���͌���݂���ꍇ�́A�[�����60mm�ȓ��̈ʒu�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
3.5.5.1 �@���C���V�[�g�̂Ƃ���́A�K��3.2.6.1�y�ыK��3.5.3.8�ɂ�鑼�́A���R�Ƃ���B
3.5.5.2 �@�_�E���z�[���B�_�E���z�[���̈�[�̃��[�v���̓��C���́A�u�[���E�W���[�̓�����
��200mm���z���Ȃ��u�[���Ɏ~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�_�E���z�[���́A�}�X�g�̃N���[�g�ɌŒ肵�Ȃ���
�Ȃ�Ȃ��B�@�_�E���z�[���́A�~�h�V�b�v�t���[���̌�����璲�߂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.5.3 �@�X�v���b�g�̉��[�́A�}�X�g�Ɏ~�߂邾���ł���B�X�v���b�g�̉��[�̑��u�ƁA���߂̕�
�@�́A���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��F
(a)�@�@����̊|����Ɋ֘A�������[�v��̃��[�v�A���̓��C���[���[�v�B����̊|����̍ő吡�@�F
�@�@�@�@�����@�@�@�F�@�@�@150mm�@�@
�@�@�@�@���@�@�@�@�F�@�@�@ 20mm
�@�@�@�@�����@�@�@�F�@�@�@�@3mm
�@�@�@�@���̍����F�@�@�@�@ 10mm
����
(b)�@�@�Q�ȓ��̃V���O���E�u���b�N�œ�d�̑��͑��u�ɂ����Q�̕����ȓ��̃��[�v�A���̓��[
�@�@ �v�ƃ��C���[��g�������n�����[�h�ƁA�P�̌����̓}�X�g�ɌŒ肳��P�̃A�C�ƂP��
�@�@�@�@�̃N���[�g�A�X�v���b�g�̉��[���̓}�X�g�Ƀu���b�N����t������@�́A���R�ł���B
�@�@�@ �X�v���b�g�́A�~�h�V�b�v�t���[���̌����蒲�߂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
3.5.5.4 �@�A�E�g�z�[���B�A�E�g�z�[���́A�P�{�̃��[�v�łȂ���Ȃ炸�A�����P��̍ޗ����琬
��˂��Ȃ�Ȃ��B�A�E�g�z�[���́A�����\�Ȃ��̂Ƃ��Ă��悢�B���̏ꍇ�A��d���͈ȓ��̂��̂ł�
����Ȃ炸�A�u���b�N���g�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����āA�A�E�g�z�[���E�G���h�́A�u�[���[��
�i�K��3.5.3.5�Q�Ɓj�̋߂��̌����͌Ŕ��p�A�C��ʂ�Ȃ���Ȃ炸�A�u�[����̃A�E�g�z�[��
�E�N���[�g�Ɋm���Ɏ~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3.5.5.5 �@�u�[���E�_�E���z�[���A�X�v���b�g�E�n�����[�h�y�уV�[�g�E�u���b�N��t���邽�߂�
�u�[�����X�g���b�v�������āA���C���[�̎g�p�́A�֎~����B
3.5.5.6 �@�����j���O�E���M�����A����X�p�[�ɒʂ��Ă͂����Ȃ��B